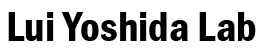2025年4月18日20:00~21:00に実施したイベント「より良い学振申請書(DC1/DC2)を作ろう」はありがたいことに非常に好評でした。動画や資料はこちらで公開しています。
個別にフィードバックがほしいという意見もあったのですが、自分のリソース的に厳しいのが正直なところです。ただ、生成AIの性能がかなり高くなってきているので、ある程度のフィードバックはできるのではないかと思い、自分の経験知を含めた学振申請書の添削プロンプトを作成してみましたので、実例も含めて公開します。
注意
- 利用する生成AIモデル・サービスによってはデータが学習されたり、サーバに一時的にデータ保存されたりします。そのため、利用にあたっては自己責任でお願いします
- 比較した結果、個人的には Claude 3.7 Sonnet は無料でも使えますし、基本的にデータは学習されませんし(参考サイト)、性能的にもおすすめですが、自己責任でお願いします
- 主な生成AIサービスのデータ学習に関するデフォルト設定や設定の変更方法などについては、教育×生成AI ポータルサイト「Manabi AI」などをご参照ください
- 本プロンプトを利用して発生した、いかなる不利益も吉田は責任を負えませんので、その点ご了承ください
- 生成AIの出力を鵜呑みにしてはいけません。デタラメをいうこと(ハルシネーション)があるので参考意見程度に捉えて、自分なりに出力を吟味してください
プロンプト
なぜこのプロンプトにしているかについては、イベント「より良い学振申請書(DC1/DC2)を作ろう」の資料や動画をご確認ください。
点数配分はかなり適当に決めているので、適宜調整してください。
プロンプトを削って評価してもらいたいところだけに絞れば、より詳細なフィードバックが得られるかもしれません。
添付の研究計画について、以下の観点で評価およびフィードバックしてください。
ただし、修士学生が書いた博士課程における研究計画書であること、紙面が限られていることを考慮してください。
* 社会的な課題や学術的な課題がわかりやすく記述されているか?(5点満点)
* 課題を踏まえて、提案する研究の着想に至ったストーリーが論理的かつ具体的に記述されているか?(5点満点)
* 研究目的は研究内容を全て包括するような目的が記述されているか?(5点満点)
* 研究方法・研究内容について、
* 何を、どこまで明らかにしようとするのか明確か?(3点満点)
* 目的に対して整合性のある方法を用いているか?(5点満点)
* 具体的に何をするのかに加えて、なぜそれをするのか含めて記述されているか? 他の方法ではなく、なぜ提案する方法を用いるのかが記述されているか?(3点満点)
* 研究の特色・独創的な点について、他の研究でもやられていない、自分の研究の独創的なところが記述されているか?(5点満点)
* 本研究の完成時に予想されるインパクト、将来の見通しについて、実際に研究が上手くいった時の具体的な社会的なインパクトや学術的なインパクトが記述されているか?(5点満点)
* 概念図について、研究計画のコアになるところや実験などの概念図がわかりやすく作成されているか?(5点満点)
* 研究遂行力の自己分析について、
* 自身の研究遂行力・強み(研究における主体性、発想力、問題解決力、知識の幅・深さ、技量、コミュニケーション力、プレゼンテーション力など)について、研究プロセスや成果と紐づけながら、具体的なエピソードが記述されているか?(5点満点)
* より良い研究者になるために今後取り組みたい内容が具体的に書かれているか? 自分にとって必要な要素を具体的に挙げて、どうその要素を獲得していくかが記述されているか?(5点満点)
実際に使ってみた
以下に、吉田の申請書(公開ページ)を主な生成AIモデルで添削してもらった例の共有リンクを記載します。全ての例をこのページにも記載すると長くなってしまうので、Claude の結果をリンクの後に貼ります。
ただし、吉田の申請書は10年以上前のフォーマットであり、これまでの研究とこれからの研究を書かなければいけなかったので、これからの研究にフォーカスするようにプロンプトを少し修正しています。
ChatGPT は個別に設定をしないとやりとりが今後学習されてしまう可能性がありますし、Google の Gemini 2.5 Pro は Google AI Studio で無料利用するとデータが学習されてしまう可能性があるので、その点ご注意ください。
Claude 3.7 Sonnet
https://claude.ai/share/1009c472-b134-42f8-aad8-5e71f5029b51
ChatGPT 4o
https://chatgpt.com/share/68054c46-3274-8013-851f-44312e107b1a
ChatGPT o3
https://chatgpt.com/share/68054aba-0888-8013-a85e-30f1145eb4aa
Gemini 2.5 Pro(Googleアカウントでログインが必要)
https://aistudio.google.com/app/prompts/1BHMxcyySFJpjiSBA0IzdBM1tTnI69rbg
以下は Claude 3.7 Sonnet の回答です。
I'll evaluate the research plan based on the criteria you've provided.
## 社会的・学術的課題の説明 (4.5/5)
研究計画書は、てんかんという神経疾患の社会的課題を明確に説明しています。特に、約100万人の日本人患者のうち30%が薬物治療に反応しない難治性てんかんであることを具体的な数字で示している点が優れています。また、迷走神経刺激法(VNS)という新たな治療法が注目されているものの、そのメカニズムが解明されておらず、効果予測と最適な刺激方法が確立されていないという学術的課題も明確に示されています。一方で、脳の情報処理メカニズム解明という大きな課題から、小規模神経回路の研究へ、そして迷走神経刺激法の研究へと繋がる論理展開がもう少し明確だと、さらに良かったと思います。
## 研究着想に至るストーリーの論理性 (4.5/5)
研究の着想に至った経緯は、解剖学・病理学的知見とMEA基板の特性という2つの要素から論理的に説明されています。迷走神経が孤束核、青斑核、縫線核、海馬という経路で繋がっていることを示し、さらに青斑核と縫線核がVNSの効果に関与しているという先行研究に基づいて、これら3つの部位(青斑核、縫線核、海馬)の相互作用を調べることの重要性を論理的に説明しています。また、MEA基板が多点計測や長期培養に適しているという特性も説明されており、研究方法の選択理由が論理的です。
## 研究目的の包括性 (4.5/5)
研究目的は「難治性てんかん、薬物抵抗性うつ病に対して治療効果が得られている迷走神経刺激作用の機序を解明することと、電気刺激条件の最適化を行うこと」と明確に記述されています。この目的は後述の研究内容(4つの実験)を包括しており、「何のために研究するのか」が明確です。ただし、うつ病に関しては背景説明には触れられているものの、研究方法の中での扱いがやや不明確である点がわずかに減点要素です。
## 研究方法・内容の明確性
### 明らかにしようとする点の明確さ (3/3)
4つの実験が提示され、各実験で何を明らかにするかが具体的に記述されています。特に「青斑核と縫線核への電気刺激が海馬の自発活動と抗てんかん性にどのような影響を与えるか」、「関係するシナプスメカニズム(神経伝達物質、受容体、遺伝子発現)の特定」、「最適な電気刺激条件の検討」など、明らかにしようとする点が具体的です。
### 目的との整合性 (4.5/5)
研究方法は目的(迷走神経刺激作用の機序解明と電気刺激条件の最適化)と整合性があります。特に、in vivoでは難しい電気刺激効果の直接観察をin vitroで行い、シナプスメカニズムの特定まで行うという方法は目的達成に適しています。ただし、薬物抵抗性うつ病に関しては、研究方法でうつ病関連の評価項目がやや具体的に記述されていない点が若干の減点要素です。
### 方法選択の理由付け (2.5/3)
MEA基板を用いる理由(多点同時電気刺激・計測が可能、長期培養可能、非侵襲的、薬理操作も容易)は明確に説明されています。また、3部位を共培養する理由(相互作用を評価するため)も説明されています。しかし、他の代替方法との比較や、なぜこの方法が最適なのかについての説明がやや不足している点が減点要素です。
## 研究の特色・独創性 (4.5/5)
「従来の研究の多くは迷走神経刺激作用を生体内で検証してきたが、実験環境を人為的に調節することが困難であることから、刺激による生体応答反応のみを評価することは困難であった」と従来研究の限界を明確にした上で、「本研究では当該作用において重要な役割を果たしている青斑核、縫線核、海馬をMEA基板上で再構築し、長期的な培養と多様な刺激条件で電気刺激を与えて計測を行う」という独自のアプローチを提示しています。in vivoとin vitroの違い、単独培養と共培養の違いも説明されており、独創性が明確です。
## 研究のインパクト・将来展望 (4.5/5)
研究が成功した場合のインパクトとして、「迷走神経刺激の中心的な作用のメカニズム、青斑核、縫線核に対する刺激条件の最適化が期待できる」と述べ、それが「患者に対してVNSを適用する際の電気刺激条件の参考になる」とし、「従来以上の迷走神経刺激による症状軽減が期待でき、これは患者の生活の質(Quality Of Life)向上に直結する」という具体的な社会的インパクトを示しています。また、「神経調節物質であるノルアドレナリン作動型ニューロンを含む青斑核、セロトニン作動型ニューロンを含む縫線核を扱うため、神経調節物質の海馬への作用機序の解明という基礎的観点からも大きな研究成果に繋がる」という学術的インパクトも示しています。さらに研究の発展性として「孤束核を含めた培養系に拡張する」可能性も言及しています。
## 概念図のわかりやすさ (5/5)
概念図(図6と図7)は非常に明確です。特に図7は生体内の神経ネットワークとMEA基板上に再構築する神経ネットワークを対比させて示しており、研究の全体像が一目でわかります。MEA基板の電極配置やシリコンブロックの構造なども視覚的に理解しやすく、研究計画のコアになる部分を適切に図示しています。
## 研究遂行力の自己分析
### 強みの具体的エピソード (4/5)
研究遂行力として、「コミュニケーション能力」「ファシリテーション能力」「計算機に関する知識・技術」の3点を挙げ、それぞれについて具体的なエピソードを記述しています。特に、他の研究生の研究支援、新入生のための勉強会の企画・実施、実験環境整備など、実際の行動と成果が示されています。ただし、これらのエピソードと自身の研究成果との結びつけがやや弱い点が減点要素です。
### 今後の取り組み (4/5)
「自身の堅実な調査と専門的知識により設定した問題に対して、幅広い選択肢の中から解決手法を決定し、環境整備をした上で効率的に研究を進め、様々な研究者と臆することなく議論し、研究を洗練させるよう努める研究者を目指す」という目標が示されています。これは先に述べた自身の強みを活かした目標設定であり、良いと思います。ただし、改善すべき弱みや具体的な能力獲得方法についての言及がやや少ない点が減点要素です。
## 総合評価 (45.5/51)
研究計画書全体として、社会的・学術的課題の提示、研究着想のストーリー、研究目的・方法の明確さ、研究の特色・独創性、予想されるインパクト、概念図のわかりやすさなど、ほとんどの評価項目において高いレベルで記述されています。特に概念図の質が高く、研究計画の全体像を視覚的に理解しやすい点が優れています。
改善の余地としては、以下の点が挙げられます:
1. 薬物抵抗性うつ病に関する研究方法の具体的な記述の追加
2. 他の代替方法との比較による方法選択の根拠の強化
3. 自身の弱みと改善計画の具体的な記述
しかし、これらは紙面の制約を考慮すれば許容範囲内であり、全体として非常に質の高い研究計画書だと評価できます。特に、社会的課題(難治性てんかん)から出発し、具体的な研究方法と独創的なアプローチを示し、その成果が患者のQOL向上に繋がるという一貫したストーリーが説得力を持っています。
使ってみた感想
モデルの自分なりの評価をいうと、Claude 3.7 Sonnet と Gemini 2.5 Pro はいい感じ? ChatGPT o3 はかなり厳しめ、ChatGPT 4o は甘い印象でした。
Gemini, Claude, ChatGPT o3 が指摘しているように、研究者として今後行うことについては具体性に欠けています(そもそも昔の申請書が要求している事項が異なるため)。その点、上記3モデルは評価基準に合わせてある程度正しく評価できているように見えます。
総合的に見ると、最初にも書きましたが、無料で使えますし、基本的にデータは学習されませんし、Claude 3.7 Sonnet を使うのが良さそうな気がしています(プロンプトを変えたら他のモデルの方が良いときもあるかもしれません)。
おわりに
もしよろしければみなさん使ってみていただき、その感想を「#学振添削プロンプト2025」などでポスト(ツイート)いただければ、みなさんのリアクションがわかるのでありがたいです!