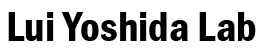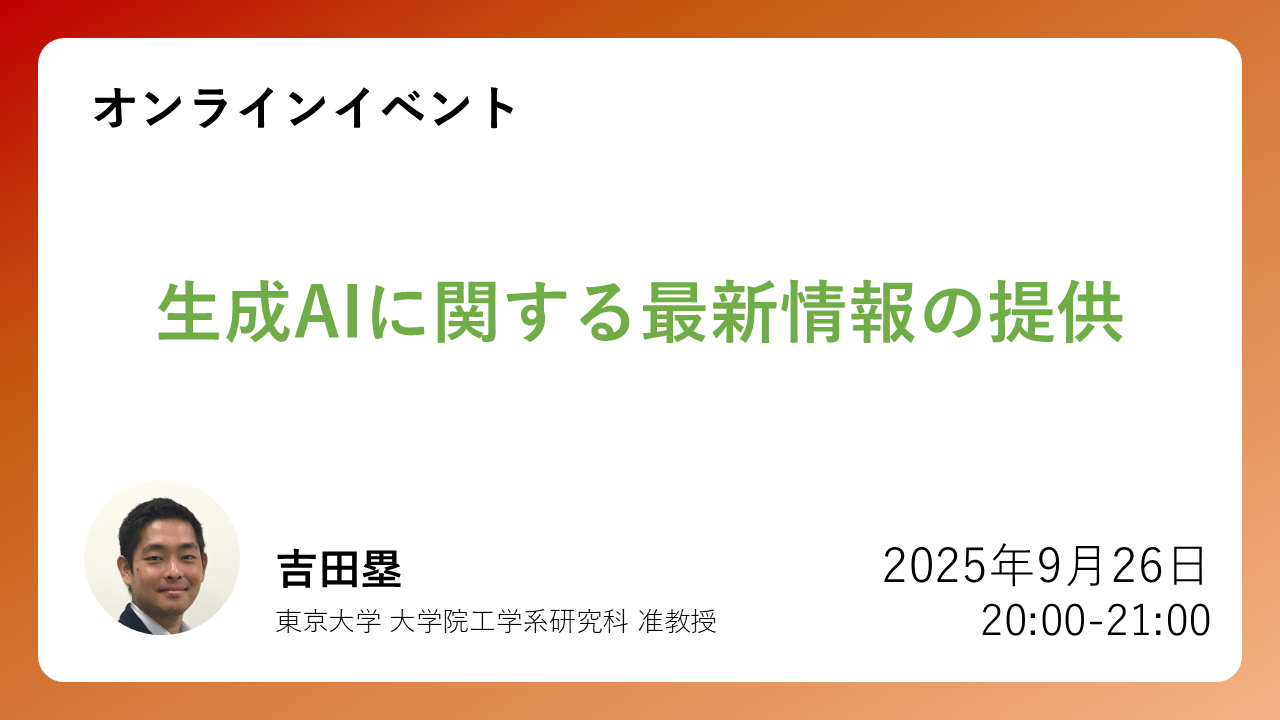2025年9月26日20:00~21:00に、イベント「生成AIに関する最新情報の提供」(開催の広報記事)を開催しました。この記事では、その開催報告と振り返りを記述します。
目次
概要
本イベントでは、教育分野を主として生成AIに関する最新動向をご紹介しました。
これまでのイベントを通して多く寄せられた、更新頻度の高い生成AIについて情報のキャッチアップが難しいというお声を踏まえ、できるだけかみ砕いて生成AIに関する最新動向を解説しました。
イベントでは新たにリリースされたサービス(Nano Banana)等の実践も行い、大変盛り上がりました。
資料(スライド・動画など)
LearnWiz One(意見交換用テキストツール)
アンケート
アンケート結果の一部をこちらに記載いたします。YouTube の最大同時視聴者数は 56名で、15名の方が回答してくださいました。
イベントの全体評価

イベントの良かったところを教えてください
- 新たなサービスの実演があり、分かりやすかったです!
- 教育とAIの切り口で、教育関係者が多く参加しているところ。
- なかなか時間が合わず参加できませんでしたが
- 色々なレベルの人が気軽に聞ける雰囲気でした。コメントも読んでもらえて、とても嬉しかったです。
- 文部科学省の「生成AIの利用について」はなかなか見れていないので、注意喚起いただき助かります。Geminiの画像編集も試してみたいと思いました。
- 新しい情報、トレンドを教えていただけること。
- 最新情報が毎日すごいスピードで変わっていて一人では追い付くのが大変なので、このように毎月情報を教えてくださる場があってありがたいです。
- 直近のアンケート結果の共有、Nano-bananaの実践、日本政府の動向など盛り沢山な内容
- 最新情報をわかりやすく定期的に伝えていただけるところです。
- Nano Bananaをはじめ、あまり使っていなかったサービスについても取り掛かるきっかけになったのが良かったです
- 実演しながら解説してくださるのでわかりやすいです。
- 時間通りに終わった所(^^)。最新情報をありがとうございます。
イベントの改善できるところを教えてください
- 実践的な事例、また海外の教育機関の事例もあるとうれしいです。
- ありません
- 盛り沢山な内容だったので、大変有意義な時間でした。今回初めての参加だったので、特に改善点は思いつかなかったです。
- ありません
- 現状、特に感じません
今後扱ってもらいたい生成AI関連のテーマ
- 数個の生成AIサービスに同じプロンプトを打ち込んで、どういった出力の違いがあるのか見てみたいです(有料・無料問わず)
- 学生のシラバス事例(生成Aiの講義)
- 画像生成はおもしろいので 参考になります
- 小学生でもGeminiが使えるようになりましたが、市教委に止められています。どんどん使える学校との差が広がっているようで焦ります。実際は全国的にどのような状況なのか知りたいです。
- 日本の会社で開発されている生成AIと学校現場での活用の可能性について
- 発言していた方もいらっしゃいましたが、n8nは気になっていました。生成AI関係の話になるとどうしてもChat GPTやGoogle Geminiが中心になってしまいますが、cursorなどかなりのサービスが使われている現状を考えると、いつもでなくてもたまにはそういう各種サービスを幅広くピックアップする回があっても良いのかもしれないと感じました。
- 最近、n8nは簡単に感覚的に使えるとゆう噂だけ聞いたのですが、調べても情報がなく、もし優先度があがってきたら教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。
- Google Notebook LMの利用について
振り返り
1ヶ月でも多くのアップデートがありました
1か月分の最新情報で1時間持つかどうか少々不安でしたが、色々な方面でアップデートがあったこともあり、ちょうど良い時間だったと感じております。
以前よりも各社のアップデートや関連技術の進展が早くなっている印象を持っています。
また、今回の評価結果は非常に高く、実施して良かったと感じています。
やはり、最新情報のニーズは高いことを改めて感じました。
今後も継続的に実施していきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
おわりに
ご参加いただいたみなさま、ありがとうございました。
これからもより良い学びの環境を提供したいと思っておりますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
東京大学大学院工学系研究科 准教授 吉田塁